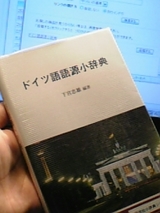2016年9月の中旬。
ニューヨークに行く、ということが決まって、村上春樹訳の『キャッチャー・イン・ザ・ライ』を再読。ニューヨークが舞台になってるのでイメージトレーニングのつもりで読み始めました。セントラルパークに行ったらあの池やメリーゴーランドを見てこようと目論んだのです。村上春樹の訳で読むのは確か2回目。底本が同じである『ライ麦畑でつかまえて』(訳:野崎孝)は大学時代に読んだはずだけどほぼ記憶なし。
ニューヨークに行くことが決まってから出発まで4日しかなかったので読み終わらず、飛行機の中でも読んでました。(僕は本を読むのが遅い)
17歳のホールデンが寄宿制の学校を退学になって、それを親に言い出せずに・・・というストーリーなのですが、たまたま、今回の旅の道連れが18歳の少年だったこともあり、小説の世界そのままのような、でも、当然ながら小説とは異なるニューヨーク旅行でした。(彼とホールデンに共通点はない)
大学生時代に読んだときの感想はもう全く記憶に無いんだけど、おそらく、そのときは主人公と自分を比較しながら読んだんじゃないかなあ。でも今回は横に少年がいたし、僕は41歳だしで主人公と自分を比較したし重ねたり、ということはありませんでした。小説の登場人物をどう捉えるかってのは年齢に関係はない部分はあるけど、ホールデンには若いゆえの行動や思考が多い気がするのでね。
ニューヨークに行くのは初めてでした。あの都会の空気は、やはりあの小説の ”いいたいこと” に合ってるなあと感じました。ほんとに都会。あの小説の舞台がニューヨークなのは、都会という人が多い場所でこそ寂寥や若さゆえの焦燥が際立つからなのでしょうね。
結局、スケジュールの都合であの冬に凍ってしまう池も、妹が好きなメリーゴーランドも見られず。きっとこれは17歳のときに見に来るべきだったのでしょう、もしくはまたもう一度ニューヨークに来なさい、ということなのかな、と思ってます。